ご意見お問合せ
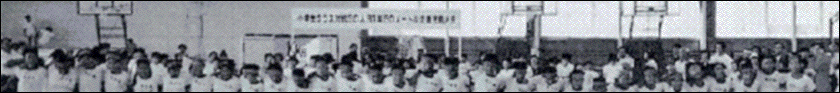
“小学校英語”を一生懸命推進している人の立場から見ると―――
なぜ反対するのか?
何が心配なのか?
どんな不利益があるのか?
・・・さっぱりわからない?
反対派の人々は、よほど”英語ギライ”かと言うと、そうではない。
むしろ、筋金入りの専門家が多い。
―――かつて数学者の広中平祐さんが面白いことを語っていた。
専門家という人種は3分以内に”それは不可能です――という理由を
20以上考え付く人のことだと言うのです!失敗事例を20も
つきつけられたら、しろうと集団は、ひきさがるしかないのです。
今回は文部科学省がその専門家集団に、まるで、たてつくかのように、
少々ゴリ押しで見切り発車するとこがおもしろい。
“おもしろい!――”というのは、普通なら、専門家集団であるお役所は、決して先には
動かないはずなのです。つまり、できない理由を20以上あげる側なのです。では、
いったいどういう力が働いているのでしょうか?
最近の説明では、産業界からの強い要請だということです。産業界が、そんなに強い力が
あるのでしょうか?大口納税者の要請だと考えればいいのでしょうか?産業界の要請は、
昨日今日の話ではなく、この30年間、要望し続け、その声は日増しに大きくなってきて
いる訳です。言い訳はいいから、いいかげんに結果を出せ!!―――と言います。
では、産業界は、今回の小学校英語を喜んでいるのでしょうか?実は震源地である
産業界こそが、相当なこの問題の専門的体験集団であり、アカデミックな議論や
手法とは又、異なる視点を持っているはずです。どうも、税金を納めていれば大丈夫だ
ということにはならないらしい?すでにトヨタのように学校づくりに乗り出した企業も
ありますが、企業が地域社会の学校づくりに乗り出すことが、何より必要な段階に
きたのかもしれません。
今回の小学校英語問題、確かに専門家筋が指摘するように、結果が出ないどころか、
大騒ぎの末、又又、大転換という道筋をたどってしまうのでしょうか?結果が出ない
どころか、挫折感や被害者意識という大きな負の遺産をかかえて再出発ということなの
でしょうか?なんとかならないでしょうか?
なんだか大きな話に聞こえてしまうかもしれませんが、実は、私の場合、小さな村、
小さな町で、私の考え方に共鳴して下さる所を探しています。
かけ算の九九のようにという発想で、この時代の難問に、ひとつの結果を出したいと
考えています。関心のある村、又は町の方からのご連絡をお待ちします。
金子詔一
Permalink